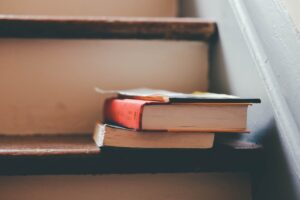今のデジタル時代、わからないことを調べたり、何か面白いものを読みたいと思ったらウェブページを検索すれば、すぐに目的の情報にたどり着くことができます。一方、私の書斎にあるたくさんの本は、一度は私に手に取られたものの、その後はずっと本棚に並び、再び私に読まれるのを静かに待っています。

本はウェブページとは異なり、まとまった内容が深く掘り下げて書かれています。何かを調べる際も、ネット上の記事は表面的なものが多いと感じます。その理由も理解できます。
なぜなら、内容が難しかったり読みにくいと、多くの人に読んでもらえないからです。多くの人がサイトを訪れることで、広告収入が得られたり、ビジネスにつながるからです。
ですから、何かを深く学び、その背景や「なぜ」を追求したいときには、本が最適です。特に「原書」と呼ばれるものは内容が深く、多くの学びがあります。ビジネス書の場合、本屋に平積みされている本の多くは、こうした原書から引用し、それを応用したものが多いのです。
原書として有名なビジネス書の著者には、ピーター・ドラッカー、ジム・コリンズ、フィリップ・コトラーなどがいます。心理学では、ジークムント・フロイト、アルフレッド・アドラー、カール・グスタフ・ユングなどが挙げられます。また、私が研究している異文化コミュニケーションの分野では、フォンス・トロンペナール、チャールズ・ハムデン=ターナー、ヘールト・ホフステードなどが代表的です。
日本でも、中根千恵さんや鈴木孝夫さんの本は、私にとって原書のように内容が深く、何度も読み返しています。

そして、ふと本棚を見て、清川妙さんの言葉を思い出しました。私の好きな清川妙さんの本の中に、「本は乗り物であり、その本という乗り物に乗って旅をすることができる」という一節があります。お会いしたことのない人たちの考えや経験にも、「本」という乗り物に乗って旅をしながら触れることができるのです。私はこの言葉が好きです。
実際に私も本を出版していますが、その内容はすべて自分の過去の体験や、そこから着想したものであり、まるで私自身の脳内を表現しているようなものです。
ですから、ふと手に取った本を、焦らずにのんびりとゆっくり読むことができたら、まるで見知らぬ土地を旅しているようで、とても幸せな気持ちになるのかもしれません。
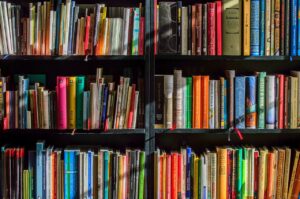
しかし、私の本棚にある本のほとんどはビジネス書で、何らかの課題があったときに購入したものです。そのため、その本の内容を急いでまとめ、課題解決のためすぐに自分のものにしなければなりません。「なんとかしなきゃ」という焦りのような気持ちがあり、一気に読んでしまいます。興味があって読むというよりも、知識を吸収しなければならないというある種の脅迫観念のようなものに駆られて、急いで読んでしまうのです。ですから、最初に手にした本は、一度読んだ後、再び読むことはほとんどありません。
私の文章の先生でもある清川妙さんは、とても情緒豊かな表現で自然や情景を描写されます。そのため、景色が色鮮やかに浮かび上がるのです。清川さんによると、一度文章を書いた後、何度も何度も見直し、句読点の位置や接続詞、表現などを改善されるそうです。そうした清川さんの本を時折手に取って読んでみると、まさに旅をしているような気持ちになります。清川さんの世界を旅し、その美しい文章に想像を膨らませるのです。
読まれなくなったビジネス書にも、著者の考えや思想が込められていることでしょう。今一度、手に取って旅してみようと思います。